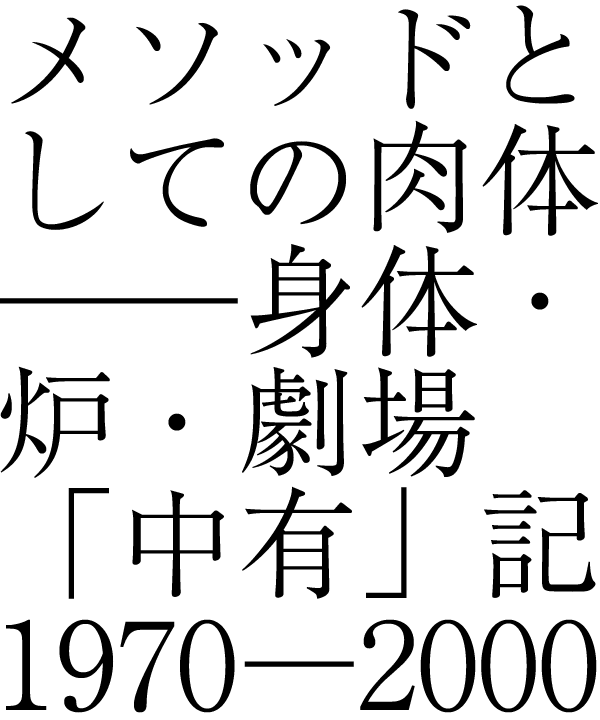芥正彦
国文学 2000年9月号、特集:演劇、映画のコンテキスト
劇場、そこは、すべてが接続可能となる極度に淫らな場処だ。また、そこは無数のたましひが消滅=生成し合う極度に空虚な場処だ。だから、もし望むなら、神の不在にケリをつけるために、「国立“心中”劇場」さえも可能になっているわけだ。
ときに俳優は他者と他者の間にあって、自ら「中有」となり、その瞬間を拡大し、延長しつづけねばならぬ。その「悲鳴」を聞き終えるまでは。なぜなら俳優はその間、つまり、世界が生成し消滅する無呼吸な切迫性の時間の中で、無数の身体をメタファーとして出現させつづける、即ち、人間でいながら人間という空虚そのものの、様々な爆発でなければならないからだ。
役所の人達が「死体」───首が無く腹部から内臓がはみ出ている───を片付げていた。
なぜか?
自分達が生産した狂人の死体だったからだ。
また、役所の人達が「劇場」───それは入口も出口ももっていない───を造っていた。
なぜか?
役所の人達が自分達の生産したいかがわしい神経症の数々を、だから自分達の狂気を、こっそり葬り去るためだったからだ。
そこで私達は、入口や出口を設け、少しは無垢なたましひが呼吸できる場処にしてやった。
今、演劇にとって、ある程度、喜ばしい事態をむかえている。自治体が税金で劇場をつくることが喜ばしいわけではない。人間の「身体」がようやく神の手や国家イデオロギーや理不尽な商業主義から分離され、人間の「劇場」に戻ってきたからだ。
さらに、経済の燃えさかるグローバルな「炉」を通過し、情報技術世界のネットを自在にくぐり抜け、出入口としての自らの身体を分離形成してはじめて喜ばしいと言えるのだが。
さて、この燃えさかる「炉」とは一体何なのだ? 人類共同性欲体をささえ、自ら呼吸さえしているものとは。
三十年前、私はある炉の中で「中有」状態にあった。眼前の白紙が殺人的に白熱する白色の嫉妬深く獰猛な白色。無限に拡大し無限に凝縮する無底の白色の只中にあって、時間が激流となって落下する白色の沈黙を引き裂き、悲鳴を電流に変える白色。この白色の「神々」、その一寸法師のような身体を燃やす、白紙の中で、わめきあう亡霊を最終的な灰にする白色の炉。
すべての「記憶」が瞬間瞬間、「形」となっては消える炎の中で、「私」という身体はダンスをしていた。灰はといえば、物質のアナグラムを繰り返し自己反復するトートロジィのエネルギィとなって一緒に踊っていた。この無時間/無空間な「炉」の内/外で、様々な機械が作動していた───言語機械、戦争機械、意味生成=死滅機械、人種混合性差変換機械、……やがて白紙自体が最終形を表す「炉」の放射した熱量剰余が世界そのものに聖的変容を起こさせ、炉の底は、底をもつことを止め、無底の、無反動の、無限無時間、無限無空間の新しい「身体」となって立ち上がった。
炉は「私」であった。それこそが、世界が世界として存するために、それを形成するすべてが接続可能な「劇場」として私を久しく誘惑していた新しい「劇場」だった!
───にも拘らず、文学空間は死者達によって、一方的に瞬時に閉じられ、外界に「倫理」として突き出していた頭部は切断され、生首となって足下に落ちた。噴出する血の海とともに新しいディオニソスとその身体ルールが誕生したのか?───「否」。
───たしかに近代日本の歴史は日露戦争を境に太平洋戦争後の東京オリンピックまで、死者達によって衝き動かされてきた歴史である。それを看て取った三島氏の計画通り、夏目漱石以来捏造されて、したがって文学を生産してきた近代自我の数々は、この三島氏の血溜りの中に落下し、多くは溺死し、その根拠と本性を見失った。───存在が転覆した。そして万博の繰り返しとジャンク文学が土砂となってその血の池を埋め立てているけれど、文学的には今もって何一つ解消している訳ではない。
さて自死への自己決定が真の決定となるには、共同体そのものの形を決定するだけの強度が必要だという。それが失われた共同体だとしても───もしそうなら。
───大衆の美が社会的毒となり、したがって精神が有機的人体に邪悪な計画を発揮し続け、共同体の存在悪を極限まで自ら自己悪として追求していく、───国語そのものに内在する「悪」を世界悪と化すような「悪」の文学が、可能なら、そしてそれが成功する刹那に、ある「中有」を境に、あるいは言語と身体の普遍的な秘密をバネにして、一転、急転直下、最高の倫理捏造となって、体制に突き出されてしまうことが、「中有存在」としての身体ならありえるだろうか?───「諾」。
なぜならそれは大量宣伝、大量殺戮装置を創出し、絶対的エロス=タナトゥスの機械「第二次大戦、原爆、神の死」として、最終戦争の名のもとに共同死の歴史を演出した体制でならば可能だろう。───氏がそう考えたとしても当然だ。
そしてそれは民の最終「悲鳴」であり、すべてを転倒したがる氏の唯一の贅沢だ。そして私の唯一の靴の中の小石だ。私の「劇場」における氏との出会いは、生存の痛点への接続と乖離でもある。その小石は重力を帯び、ブラックホールのようなものに変化しつづけてきている。
───ところで祖国とは何だ?
いかなる存在が共有可能なる時間を生成しているというのだ? それは誕生と埋葬が等しくなるような「時間」への急速な自己合一の欲求のうちにあるのではなかろうか。
もしそうなら愛人と心中した有島武郎は自分にふさわしい純粋=祖国に入ったのだ。母親殺しをする十七歳の少年もかすかな祖国を要求し、そうしたのだ。そして無数の小さな存在消滅時間とそれからとび出す小殺人者達はいかなるものとの接続も拒みつづけて、トリスターノさながら金輪際をも通過してめでたくアラヤーシキへと完全脱出するという訳か?
これは三島氏が自らの「空虚と悲鳴」の最終「四部作」における、身体を収容するその“時間と存在”を開きかつ閉じるための劇場論として、歴史の残酷も、世界のすべてを「劇中劇」とみなすことができるようにするため、瞬間瞬間、永遠に万物を誕生させ、かつ埋葬しているアラヤーシキ(の一部)を大劇場論として用いたにすぎない。とすれば氏すらも、「日本」とは別な真新しい“祖国”へと、自らと自らのエクスタシーとしての分身どもを誕生させ、その悲鳴を埋葬させるべく導いていることになる。その祖国はあくまで「身体」にかかわる「空虚」として立ち現れる「時間と存在」に他ならない。
無名な、したがって国語によって命名される以前の、たえずコードからすり抜けるコード化不能とされた“何もの”かである。
したがって、無の海(豊饒の海=砂漠)で、あの月修寺の庭で衆生の岸辺から首を差し出して邪悪な老醜を自ら晒している本多繁邦を一瞥している瞬間の永遠、この無時間性の魔物と化した「聡子」の中有(=俳優)の出現こそが氏自身の身体の劇場をしめくくる、すなわち「身体無き器官体」(傍点:身体無き器官体)でしかない三島氏が二重倒錯した結果、ついに「器官なき身体」に氏自ら達し、それに触れてしまった証拠だと、今私は考える。「聡子」は、氏の生体と、すぐにでも氏によって創造されるべき死体の双方に関わる「中有」であり、俳優存在として、その相互指示体であり、「器官なき身体」のイマージュであり、その形而上学的メタファー(=鏡)にすぎない。
ともあれ、氏の文学空間は臨界に達し、「無」は沸騰したのだ! あとはすべて紙クズだけの現実界しか氏には残っていない。「神ながらの道」をタナトゥスで逆行する!
それはエロスの虐殺である。動物の事物化である。
ここで「器官なき身体」、二〇世紀にできたこの「新しい空虚」の爆発に、図らずも氏自らも関わることにいたったこのA・アルトーの身体、すなわち自らの「悲鳴」を他者としてなりひびかせる空虚の爆発の「劇場」では、瞬間瞬間、私達は生と死を往復している。したがって私達は、瞬間瞬間の「中有」を経験しているのだ。ありとあらゆるこの「中有」のみを交通させる「空虚の劇場」の発生を、この「無の沸騰点」における「倫理」の出現として、今一度みつめる必要があるだろう。───これこそが世界資本主義のフレームの中で、二一世紀を作る新しい「劇場」の出入口として新しい「身体」の発見となるからだ。
───ところで「中有」って何だ?
私がこんな事をいうのがふしぎだが(ふつうは死んで生まれ変わるまでの存在を言うが)私は「中有」というものを、「劇場=この身体という空虚」を飛び回る存在の(演劇の)影や分身と呼んだA・アルトーから学んだ。
A・アルトーは若い頃にダライラマから学んだらしい。私は現前を、だから衆生の輪廻をみつめ、自らの転生を絶対的に拒む大いなる「中有」(もしあるなら)の仕事が俳優の仕事だと確信している───
今日、───三十年前、私の眼前で私という「炉」に発生した無時間無空間の諸機械が、似て非なるものではあるが惑星規模で地上に転回してしまっていることに気付く。光の同時刻圏のスピードの中で、無時間/無空間を技術化した世界資本主義経済の「炉」の中に全人類が欲望機械となって入ってしまった以上、私達は「炉」であると同時に燃料でもある。すでに入口も出口もない、こののぺらっとした空間に、かつての「絶対」は無く、共同で内在し無意識の不安を安じる聖=祖国は無く、あるのは神の手(オノコノミア)から離れた「身体」だけがある。したがって、二〇〇〇年の地球史的世界史的存在論的淘汰をくぐった私達の、この「身体」だけがこの空間の入口であり、かつ出口なのである。
「身体」を開閉するたびに真の空虚を見出し「在って在るもの」すら関与させえぬ、この「器官なき身体」には、わずらわしい生殖に関わる一切の器官から離れ(この世の幸せになろうとする悪霊どもから離れ)、グローバル化経済の炎にも燃えることなく、自らの一生が、聞こえぬ一条の悲鳴にすぎぬことすらを覚醒する永遠=瞬間の「幸せ」があるわけだ。
そして人は、この空虚の中に、もし望むなら、他人の悲鳴を聞くことができ、互いに一瞬の裡に自らの悲鳴を目撃し合う、人間は再び自らの「劇場」に達することができるのだから。そしてそれが新しい「祖国」のはじまりであるのだが。
かつて両大陸での二極にわかれてつづけられた人類の二つの共同幻想実験の結果、両イデオロギー思想が、とどのつまり、「親方不在のペニス入れ」、この性欲共同体に軍事化した重化学工業を差し込み、権力の基底材としたものにすぎず、ヒューマニズムもその国家創成のメタファーにすぎなかった以上、世界歴史はここ最近はっきりと死んだのだ。(かつて徳川時代に日本歴史は自らの死を死んでいったように。)そして世界は形成すべき身体を失った。だからといって人類は死んだわけではない。───人々は身体を失ったわけではない。欲望の無意識機械としては形成して、あるいは、されていないのだ。より自由に活発になっている、身体をもたず、共同無意識の一部として夢幻のエクスタシー器官として、経済のカマドの中で燃えているのだが、神自らが自らを犠牲に賦して誕生したかのようなこの経済無底のカマドは、炎の中で運よく自ら頭蓋骨の中の溜り水を飲めば勝利者だ。アラヤーシキなどというおとぎ話で秩序づくものではない。
人は悲惨な「悲鳴」に感づきながらも自らの白い頭蓋骨に向かって数歩この世界を歩いて終えるという「中有」にすぎず、「中有」の世界劇場に自らを発見しなおすというシンプルここに極まる法体に世界はなかったのかもしれない。
かつて思考のメタファーとしてダンスが生まれたように、生のメタファーとして様々な悲鳴がそれぞれの弔い歌を歌う無重力の宇宙空間に、「天人五衰」の実現として再集合し直してしまったのかもしれない。───
でなければ、人類全体が復活も十字架も無い、ゴルゴタの丘に化した惑星(=世界資本主義)上で手を差しのべ、ただただ自らの頭蓋骨を生産しつづけるために快感原則運動機械を運転している。パンを焼くために自らの身体を蒔にしているのがSF的実情だ。
さて他者を持たずしてこの聞こえぬ悲鳴をひっ摑み、自己痙攣を起こさねばならぬ。そしてそれが生の証で、全く秘室の、無償のいけにえ産出機械に自らがされたとしても、この世界という「身体の歴史」に自らの身体で侵入してみなければならない。
その空虚な自らの身体を基底材とした報酬とは一体何なのか?
そいつは、人生という不可能な悲鳴をひっ摑み、「炉を持った劇場」に痙攣させながら解き放ってやることだ。
そうすれば世界は聞こえぬ悲鳴の束であることを止め、ふたたび何ぴとたりとも通行可能な一つの過不足ない身体となって現前に生き返るはずだ。
演劇は全人類に共通する唯一の財産だと私は考える。それは眼前に絶えることなく現前する世界───存在の再至近距離に、かつ、最大遠方にあり、その外部と境界に同時に生起つつ、同時刻的に関与し、その境界と中心とに残留しつづけるものを、同時代的戯れと化すことができる唯一の贅沢で、「人間」による「人間」のための技法化が「人間」の手で「人間」の眼前に成される唯一の残酷だ、と考える。
三島氏の場合、(戦後体制の空虚な二重化に対抗すべく、自己の心身を二重化して耐えているうちに)ただただ文学産出機械に化しつつあった「戦争としての身体」を自己破壊したわけだが、それも、彼のエチカであり、贅沢である。強引に他者の「悲鳴」を自らのものとする故に悪徳として倒錯した残酷ではあるが、これもまた「悲鳴」の「演劇」なのだ。
アラヤーシキの先験的劇場性はもちろん言うまでもなく、「火、水、風、土」の四大が、「身体」=「炉」としての劇場の万物構成要素であったように、「炉・精神・言葉」、「父・子・精霊」、「存在・神・学」、「権力・神話・秩序」、「意味・真理・場所」、「重力・真空・恩寵」等々、皆、各々が「身体」を支える力学であると同時に演劇世界を発現する「炉」の劇場構造力学としてある。
さて、A=A、ハムレットはハムレットでありつづける、という自同律時間の内部(もしくは自然律の裏側)で、言葉が精霊と「精子」を結びつけ、「中有」としての身体を通じて、したがって意味と「卵子」が融合しあい、さらに言葉を生産させながら、自らの形を露わにしている。「演劇」は言うまでもなく、「人間」をたえず、別な地下茎を通じて、外部へ「形」にする、「エチカの構造」を持っている。
だからこそ、今日めくるめく現実的欲望を発明し、要求し、実現しようとする、共同無意識エネルギー体に衝き動かされているこの世界経済=「カニバリズム(=戦争)の劇場」の中であえて「身体」はエチカとしての「炉」をもつことになるのだ。それは、新しい「空虚」を発生させ、淘汰の歴史の上に新しい「悲鳴」を自らのそれとして聴き届ける、「身体の劇場」を眼前に誕生させることであり、カニバリズムの犠牲者群を新しく埋葬し直す「時間」を生成することである。ここにおいて、「演劇空間」は新しい「祖国」の時間をも所有し直すことになるだろう。
というのも、世界は「エチカの演劇」の基底力学によっていくばくかの自らを実現して来たのだ。「炉」に精神の火を点火したプロメテウスの劫罰は、絶対時間=零空間と絶対空間=零時間をその「身体」に引き受けたそれであり、モーゼが自らの民への嫉妬を絶対化した砂漠の獰猛な破壊構築の神を、新しい「人間」のために光と水と言葉と愛のそれへと脱=構築したイエスの磔刑も、「身体」のそれであり、同じくヒンズー教の神々を、慈悲のそれへと脱=構築したシャカのそれも、空虚が爆発する「器官なき身体」を、ヒットラーに対抗する基底材としたA・アルトーのそれも、フランス共和国を誕生させたアセファル、ルイ16世の「頭部なき身体」に象徴されるそれも、ペストによる無類の死体達の沈黙の「身体」が「神の沈黙」=教会の「身体」制をなし崩しにしたそれも、原爆の輝きに燔儀にされた「身体」のそれもアベカオルのラッパも、全共闘運動という「炉」を点火した無償制の「身体」のそれも───、皆「エチカの演劇」の力学のそれで、世界の基底力学であった訳だ。そして今、何十億という「中有」達が現実世界に、だからこの「劇場」の中で、転生を待って日々息をしている訳になる。
すでに、世界はいつもホメロス的に言って、「イリアス」であるよりは、一つの『ゴルゴタの丘』となったこの惑星を、「ユリシーズ」として動いている。したがって地球は一つが全体である『ソラリスの星』として、今動いているのだった。
ソ連が崩壊したのは「対話」が流通したからである───というのが真実であるように、今、人類共同体という大記憶装置の幻想が水蒸気のようにこの星をすっぽりと包んでいる。経済の「炉」が新しく原爆とともに点火された証に。
そして、三島由紀夫氏は小さな「ユリシーズ」をその帰還の不可能性を犯して上演し、消えていった。
ところで氏の身体はそのはじめから「身体なき器官」(傍点:身体なき器官)としてしか機能してはいなかった。当然、「天皇」とは皇室を持つが故に無数の生及び性のメタファー、即、死の影達の集合する場処であり、当然「身体無き器官」(傍点:身体無き器官)であるが故にエロスであり、倒錯したタナトゥスであり、性的共同=存在の記憶でありえたのだ。国家審美学という神の死の不安を隠蔽するための、絶対時空間を捏造する装置としての「天皇」機械であり、その「身体なき器官」(傍点:身体無き器官)を、死を入口として宇宙大に拡大し、全自然悪を呑み込んだ大殺戮機械を創造し、全人類支配の金剛=胎臓となる美のネットワークの完成と考え、青年は実行した訳だ。
この「共同異常性欲体」は、一時近代「日本」そのものとなり、共同主観存在と呼ぼうが呼ぶまいが、絶対的な自らの異常生殖を存在せしめたのだ。今では世界経済空間の中で無限に分離され水増しされてはいるが、世界が快感原則支配の「劇場」にあっては、たえずその「悪夢」は無意識を通じて「身体」の内部に立ち現れ、聴きえぬ「悲鳴」となって存在の不安を生産し、無数の神経症を発明させている。(三島氏は七〇年の地平で、この「不安の夜」に自己決着を下した訳で、その意図することは、「悲鳴」の増幅装置とすることだった。)
さて、速かに、私達は、新しい「身体」のための新しい「炉」よ急げ、光の同時刻の中へ出発だ。新しい無音の「祖国」よ急げ! なのである。
ふと振り返ると、お役所の人達は遠くから手を振っていた。いずれにしても新しい時は厳しい。私は今、燃えながら泣いている一握の灰だ。
演劇家・ホモ・フィクタス主宰───